
同じく基板、部品、定数などについて徹底解析してみる。
別項の中期型と比べてかなり音が違うので、
個体差の要因も調べてみよう。
|
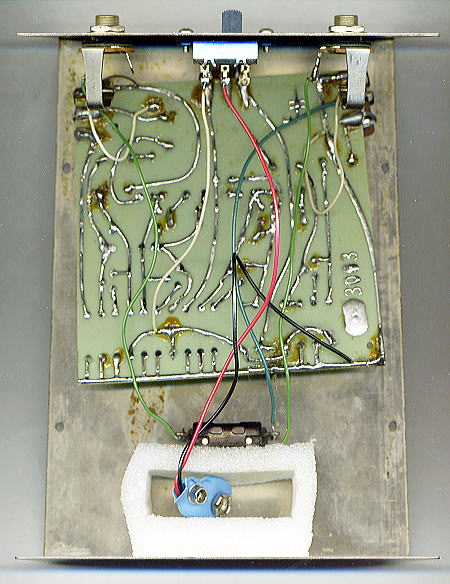
内部写真。配線は細くて折れやすい。これは現行品でも受け継がれている。
せめて取れにくいように改良して欲しいモノだ。
この頃はTONE-BYPASSが無く、全体的に線材は少なくシンプル。
|
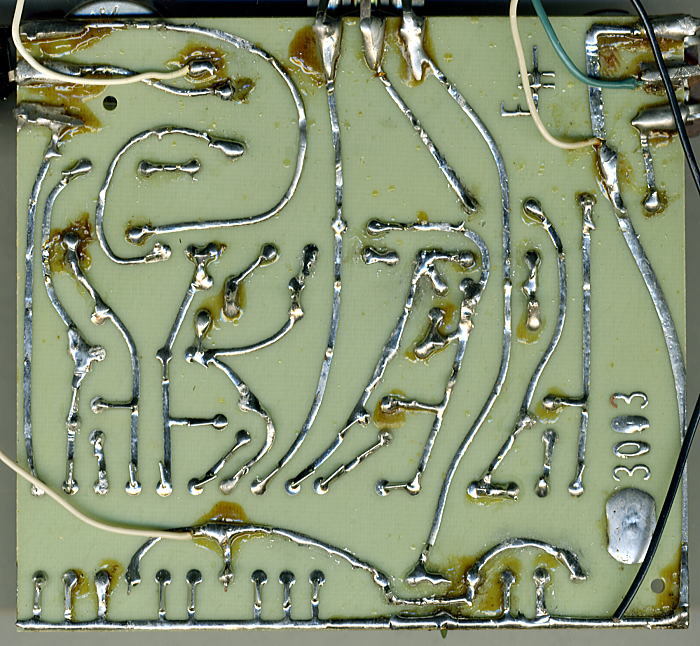
基板PCB面写真。パターンは黄色基板と同一の模様。
大きさはこの向きで、ヨコ110mm、タテ100mmだ。
|
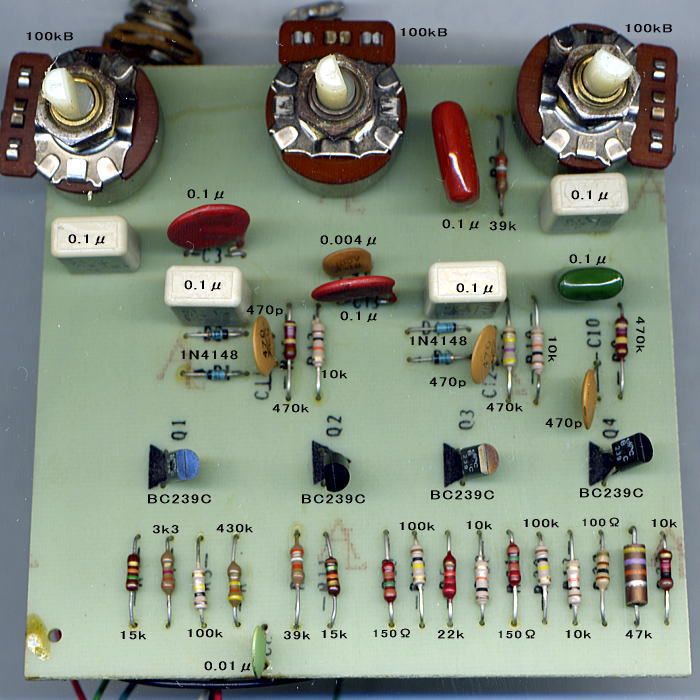
定数を採取した基板パーツ実装面の拡大写真。
別項で紹介している個体と比べ、特にコンデンサの定数違いがかなりある。
各パーツの詳細については下記に記すが、
カップリングに良く使われている1μがこの個体では全て0.1μになっている。
それに伴い、電解コンデンサが皆無!
さらには同じ0.1μでも何故か複数の素材が用いられているなど謎満載だ。
抵抗の値は、他の個体とほぼ全て同一、あるいは誤差の範囲内の近似値である。
では、以下に各パーツについて少し詳しく見てみる。
|

キモのトランジスタは、"BC239C"。
最初期の個体は頭の丸いドーム型の"FS36999"という石が使われているが、
中期以降のラムズの大多数ではこのBC239Cが用いられている。
基本的には他の用途でもポピュラーな汎用小信号用の石で、
現在でも"BC239CTA"なる改良版が販売されている。
|
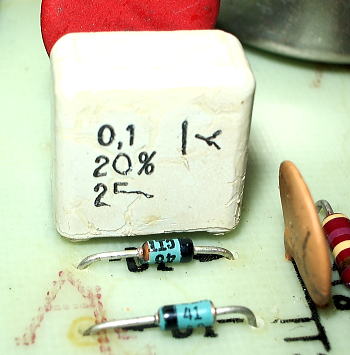
他の固体でも良く見受けられる白くて四角い0.1μのコンデンサ。
秋葉原のパーツ屋のオヤっさんに写真を見せて聞いてみたら、
「う〜ん、ポリカーボネイトかなぁ〜。全く同じのは見たこと無いなぁ。」とのこと。
|

さっきのすぐ隣に実装されている真紅の0.1μのコンデンサ。
容量は同じなのに素材が違うのはミステリー。セラミックかなぁ?
電源回路用にも見えるが、耐圧は25Vなので単に古いからデカイだけかな?
|

入力段のコンデンサ。
他の個体ではアルミ電解の10μなんてモノが付いていたが、コイツは0.1μ。
容量比なんと1/100!
しかも0.1μは他にもいっぱいあるのにコイツだけまた素材が違う。
おそらく電源回路などに良く用いられるメタライズドフィルム?
|

クリッピング・ダイオードはこれまた青い色でびっくらこいたが、
よ〜く見ると"4148"の数字。
おそらく汎用の"1N4148"で間違いなさそう。メーカーの違い?
|

抵抗は現在でも一般的に手に入るカーボンタイプが大部分を占めている。
トライアングルやラムズ初期型で多用されているカーボンコンポジション
(この写真の右から2番目の円筒形タイプ)はこの固体では一本だけ。
おそらく全体的に品質も安定しているので、音への直接的な影響はかなり少ないと思われる。
|